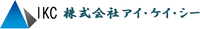「本当にこの勉強法で大丈夫だろうか…」
「どんな問題が出るのかイメージできない」
試験が近づくほど、そんな不安が強くなるのがITコーディネータ試験です。
準備を進める中で不安は尽きませんでしたが、試験当日の体験を振り返ると“やって良かったこと・工夫すべきだったこと”がはっきり見えてきました。
試験会場の雰囲気から時間配分、集中力を保つ工夫まで、リアルな受験体験をお伝えします。
これから受験を控えている方にとって、少しでも不安が軽くなり、「これなら自分もできそう」と思えるようなきっかけになればうれしいです。
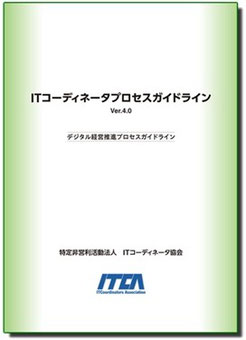
1.受験前に知っておきたかった“試験当日の流れ”
受験前の一番の不安は「当日のイメージができない」こと
ITコーディネータ試験は、単なる知識試験ではなく、ITと経営をつなぐ実務的な判断力が問われます。
だからこそ「どんな雰囲気なのか」「試験の流れはどう進むのか」といった具体的なイメージを持てないまま当日を迎えるのは、とても不安なものです。
受験前は、ITコーディネータ協会が公式に公開しているサンプル問題を読み込んでいたものの、当日のリアルに関する情報が驚くほど少ないことに戸惑いました。
ITコーディネータ協会が公式に公開しているサンプル問題
👉 https://itc-shikaku.itc.or.jp/exam/preparation/
受験当日のリアル体験
ネットでは試験範囲や参考書は紹介されていても、当日の会場の様子や時間の使い方、どんな問題が出るのかといった"体験ベースの情報"はあまり見かけません。
実際に受験して合格した体験をもとに、以下のポイントをできるだけ具体的に共有します。
- 試験当日の流れと会場の様子
- 基本問題・応用問題の印象と時間配分
- 集中力を保つための工夫と反省点
- 合格につながった勉強法と直前準備
これから受験する方が少しでも安心して本番に臨めるよう、「リアルな体験談」と「学び」をまとめていきます。
2. 試験直前の準備で得た安心感
本番前に感じていた不安とプレッシャー
ITコーディネータ試験は年に2回しか実施されないこともあり、情報が限られていて不安を感じやすい試験です。
受験が近づくにつれて、「本当にこの対策で大丈夫かな…」という気持ちが強くなり、焦りを感じる日々が続いていました。
特に、応用問題のイメージがつかめず、「本番で時間内に解ききれるのか?」という不安が大きかったです。
効果的だったのはサンプル問題の活用
そんな中で大きな支えとなったのが、ITコーディネータ協会が公式に公開しているサンプル問題でした。
これらの問題を繰り返し解き、内容を完全に「覚えてしまうくらい」までやり込んだことで、本番形式の出題に慣れることができました。
実際に効果を感じたポイントは以下のとおりです。
- 問題文や選択肢の“文量感”に慣れることができた
- 似たような表現やひっかけにも対応できるようになった
- 時間配分の感覚がつかめた(1問あたりどのくらいかかるかの目安)
結果的に、試験当日には「見たことのある問題が出てきた!」と感じる場面もあり、落ち着いて対応できました。
「完璧でなくても繰り返す」ことが安心につながる
サンプル問題は、最初から完璧に解ける必要はありません。
むしろ、間違えながらも繰り返すことで、自分の弱点や思考のクセを客観的に把握できるというメリットがあります。
これは、脳科学学習法のインプットに当たります。
特に直前期は、「完璧を目指すよりも、“本番で自信を持って解ける問題を増やす”ことを意識する」のが大切だと感じました。
3. 会場入りから試験開始までの流れ
30分前に到着して心を整える
ITコーディネータ試験当日、試験開始の30分前には試験会場に到着しました。
少し余裕を持って会場に入ることで、心の準備をする時間が取れますし、直前のトラブルや焦りを避けることにもつながります。
会場の場所は事前にしっかり確認しておくのがおすすめです。特に初めて訪れる会場の場合は、前日までにアクセス方法を調べておくと安心です。
受付・荷物の預け入れ・持ち物の確認
到着後はまず受付で本人確認を行い、指定されたロッカーにスマートフォンや荷物をすべて預けます。
ITコーディネータ試験はCBT(Computer Based Testing)方式のため、筆記用具や飲み物も持ち込み不可です。
入室後に許可されているのは、試験で使うPCと操作マウス、配布されるメモ用紙とボールペン程度です。
私は念のため、受付前にトイレを済ませておき、荷物を預ける前に水分補給もしておきました。
試験開始までの静かな緊張感
着席後、PCの操作説明をPC画面で確認します。(回答画面の見方など)。
その後、自動で画面が切り替わり、本試験がスタートします。自分で早めにスタートすることもできます。
会場内は静かで、まわりには社会人受験者が多く、独特の緊張感がありました。
少し緊張しながらも「ここまでやってきたから大丈夫」と自分に言い聞かせ、深呼吸をして気持ちを整えました。
4. 前半:基本問題40問に取り組む
出題は用語・定義・ガイドラインが中心
前半の40問は、ITコーディネータとしての基礎的な知識を問う内容が中心です。
具体的には、プロセスガイドラインに関する問題が出題されました。
内容そのものは「難解」というより、「正確な理解が求められる」という印象です。
選択肢の中には、言い回しが似ていたり、ひっかけに近いような表現もあるため、細かい部分までしっかり理解しているかが問われる構成だと感じました。
時間配分は「1問1分」を意識して
この基本問題に関しては、「1問あたり約1分弱」で進めることを目標にしていました。
実際には30分ほどで全40問を一通り解き終えることができ、「後半に余裕ができた」と安心したのを覚えています。
この時間管理ができたのは、事前に繰り返しサンプル問題を解いていたことが大きかったです。
サンプル問題を徹底的にやり込んだ成果
ここで特に手ごたえを感じられたのは、ITコーディネータ協会が公開しているサンプル問題を“ほぼ暗記レベル”まで繰り返していたからです。
実際、本番でも見覚えのあるパターンが多く出題され、「あ、これは練習でやった内容だ」と自信を持って解くことができました。
さらに、サンプル問題を通して「どんな言い回しで問われるか」「どんな選択肢がよく出るか」といった出題パターンにも自然と慣れることができ、本番での不安を大きく減らすことができました。
5. 後半:応用問題で集中力との勝負
ケーススタディ形式の問題に切り替わる
前半の基本問題が終わると、残りの60問はすべて応用問題(ケーススタディ形式)になります。
ここでは、経営者や現場からの相談や課題が提示され、それに対してITコーディネータとしてどのように対応すべきかを選択するスタイルになります。
問題文の分量は基本問題とさほど変わりませんでした。
ただし、読解力と集中力の勝負に変わります。
問題文の分量は、ITコーディネータ協会が公開しているサンプル問題が参考になります。
似たような選択肢に迷いやすい
応用問題では、選択肢がどれもそれらしく見えるため、どれがベストな回答なのかを迷う場面が多くなります。
特に、言葉の違いが微妙なケースや、「一見正しそうだけど論点がズレている」ような選択肢が混ざっているため、しっかりと文脈を読み取る力が必要です。
なので、途中から集中力が切れてしまうこともあります。
後半に入ってから明らかに読むスピードが落ちてしまい、苦戦しました。
ペースダウンと時間切れのプレッシャー
基本問題を30分で終えた時点で、「残り90分で60問ならいけそう」と感じていたのですが、それは甘かったです。
応用問題は1問ごとの時間消費が大きく、しかも途中から集中力の低下と疲れが一気に押し寄せてきました。
さらに悪いことに、試験直前に持参していた滋養強壮剤を飲み忘れていたことにも気づき、「もっと集中力を保てたはずなのに…」と後悔もありました。
時計を見ると、残り10分で10問という厳しい状況に。
なんとか頭をフル回転させて解き進め、最終的には試験終了の3秒前に送信ボタンをクリックするという、ギリギリの滑り込みでした。
6. 結果発表とそのときの気持ち
試験直後の緊張と不安
すべての問題を解き終え、送信ボタンを押した瞬間、手が汗ばんでいたのを覚えています。
「間に合った…!」という安堵と同時に、「果たして合格ラインに届いているのか」という不安が一気に押し寄せてきました。
ITコーディネータ試験はCBT方式のため、試験終了後すぐに画面に点数が表示されます。
この「その場で結果がわかる」というのは便利ではありますが、緊張感もひとしおです。
合格の2文字に思わず深いため息
画面に表示されたのは合格基準点を超えたスコア。
その瞬間、胸の奥にあった不安が一気に解放されて、思わず深いため息が出ました。
「やってきたことは間違っていなかったんだ」と心から思えた瞬間です。
合格につながったと感じる要因
今回の試験を振り返って、合格につながった大きな要因は以下の3つだと思っています。
-
サンプル問題を徹底的にやり込んだこと
→ 出題形式や文量感に慣れ、本番でも焦らず対応できた -
時間配分と優先順位を意識して進めたこと
→ 特に前半で時間を稼げたのが後半に活きた -
「読んで理解する力」を普段から意識していたこと
→ 応用問題にも冷静に向き合えた
もちろん反省点もありましたが、全体として「事前の準備が本番での安心感を生む」というシンプルな原則の大切さを、改めて実感する結果となりました。
7. 今だから言える「戦略的な解き方」
集中力の高い時間帯をどう使うか
今振り返って思うのは、試験前半の集中力が高いうちに応用問題を先に解く戦略もアリだったかもしれないということです。
応用問題は選択肢も似ており、集中力と読解力が問われるため、脳が元気なうちに取り組んだ方が判断力が鈍らずに済んだ可能性があります。
実際、後半に応用問題に突入したとき、集中力が切れて読解スピードが落ちてしまいました。
「一発勝負の試験」だからこそ、最もパフォーマンスが出せる時間をどこに使うかが重要です。
時間配分は「柔軟に、でも意識的に」
前半40問の基本問題は、ITコーディネータ協会が公開しているサンプル問題でしっかり対策していたこともあり、比較的スムーズに解けました。
そのため、ここはあえて早めに終わらせて、後半に時間を多く残す戦略が有効です。
「1問1分」を目安に解き進め、約30分で基本問題を終わらせることができたので、応用問題に90分を確保できました。
この判断自体は良かったと思っています。
ただし、実際の応用問題では想定以上に時間がかかり、「もっと余裕を持っておけばよかった」とも感じました。
特に迷う問題も多かったため、基本問題は「1問30秒」程度のペースで進められるようにしておくと、さらに安心だったかもしれません。
もし、サンプル問題を完全に覚えておくレベルまで仕上げていたら、基本問題は20分で終わらせ、応用問題に100分割くという配分も現実的だったと思います。
大切なのは、自分なりの時間の目安を持っておくこと。
そして本番では、「このペース、ちょっと遅れてるかも」と気づいたら、一旦飛ばして後回しにする判断力と柔軟性が、試験全体のパフォーマンスを左右します。
メンタル面の準備も「戦略」のひとつ
集中力を長く保つには、試験当日の体調管理も含めたメンタル戦略が欠かせません。
私の場合、直前に飲む予定だった栄養ドリンクを忘れたことで、後半の粘りが弱くなったと感じています。
また、緊張しやすい人は、試験前に繰り返し「模試のつもりで通しで解いてみる」体験をしておくこともおすすめです。
本番で初めて通しで問題を解くと、想像以上に疲れるため、体力と集中力の配分も事前に体感しておくと良いです。
8. 出題内容の印象と傾向
全体として「幅広く、実務寄り」
ITコーディネータ試験は、特定の分野に偏ることなく、プロセスガイドラインVer.4.0の第1部を理解していることを前提に、第2部・第3部・第4部からバランスよく出題されていると感じました。
出題内容は、経営戦略、デジタル経営実行計画、IT開発・導入、価値提供・運用、提供価値検証、サイクルマネジメント、コミュニケーション、モニタリング&コントロール、セキュリティ、組織学習といった実務全般に広がっており、まさに「幅広い知見」が求められる構成です。
いわゆる“技術者向け”の試験というよりは、ITと経営の橋渡しを担う人材を評価する試験という印象が強く、経営者との対話や支援を想定した判断力・実務感覚が問われる点が特徴的です。
サンプル問題との一致度は高め
本試験を通じて特に感じたのは、ITコーディネータ協会が公開しているサンプル問題と、本試験の構成や文量が非常に近いということです。
設問の文体や、選択肢の言い回しもサンプル問題とよく似ていて、あらかじめ見慣れておくことで心理的な余裕が生まれるのは大きなメリットです。
初見の問題でも、「この形式、サンプルで見たことある」と思えるだけで、落ち着いて対応できました。
ただし、サンプル問題が全体を完全にカバーしているわけではありません。
本試験では、似た内容の選択肢が並ぶ中から正確に判断する力が求められる場面も多く、単に暗記するだけではなく、内容の本質を理解しておくことが大切だと感じました。
出題形式について
問題形式は、大きく分けて次の2種類があります。
- 単純な4択問題
→ 1つの設問に対して、最も適切な選択肢を1つ選ぶ形式。
→ 基本問題(前半40問)に多く出題され、用語や定義の正確な理解が求められます。
問題:ITコーディネータが果たすべき役割として、最も適切なものはどれでしょうか。
1. プログラミング作業を代行すること
2. 経営課題の解決を支援すること
3. サーバー機器の運用保守のみを担当すること
4. 社内の経費精算業務を行うこと
- 複数の組み合わせが4択になっている問題
→ 複数の選択肢の正誤を判断し、その組み合わせが提示された4択の中から正しいものを選ぶ形式。
→ 応用問題で多く出題され、細かい知識と判断力を同時に問われる特徴があります。
問題:以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれでしょうか。
a. サイクルマネジメントは、継続的な価値創出を目的とする。
b. プロジェクトマネジメントは、単一のプロジェクトの成功を目的とする。
c. サイクルマネジメントとプロジェクトマネジメントは、目的も対象範囲も同じである。
d. サイクルマネジメントは、価値実現サイクルの活動と密接に関連している。
1. a, b
2. a, c
3. b, c
4. a ,b ,d
特に組み合わせ問題は、選択肢単体では理解できても、全体の組み合わせで考えると迷いやすいのが難点です。
そのため、サンプル問題で正誤判断の練習をしておくことが、本番での対応力を高めると感じました。
応用問題では「読解力+実務的な視点」がカギ
応用問題に関しては、単なる知識では対応できない場面が多く、与えられたケースに対して“ITCとしてどう判断するか”を問われるような設問が多かったです。
ここでは、現場の課題理解・経営者視点での助言ができるかどうかが試されます。
特に後半は集中力が落ちやすい時間帯なので、読解に慣れておくこと、時間に追われても焦らず読み取る訓練が重要だと感じました。
9. 印象に残った出題カテゴリの具体例
変革・成長プロセス(P1)
- デジタル経営戦略プロセスからのフィードバック
- デジタル経営成長サイクルと価値実現サイクルの順序性と自律性
- デジタル経営成熟度レベルが0,1,2のときの目標レベル
- デジタル経営戦略プロセスからフィードバックを受けるデジタル経営戦略達成度評価の内容
など、サイクルを意識させる設問がありました。
経営の全体像をどう捉えるかが問われるカテゴリです。
デジタル経営戦略プロセス(P2)
- デジタル経営を支える人材としてのデジタル経営推進者の役割
- デジタル経営戦略プロセスの活動
- 経営環境情報の収集方法
- データ・IT 利活用方針の定義のアウトプット
- デジタル経営戦略達成度評価のインプット
- 経営環境情報の収集方法
- データ・IT利活用方針の定義
経営戦略とIT活用をどう結びつけるかを理解しているかがポイントでした。
デジタル経営実行計画プロセス(P3)
- 価値実現サイクルからデジタル経営戦略プロセスへのフィードバック内容
- デジタル経営実行計画プロセスの活動
- データとIT の調査の対象
IT開発・導入プロセス(P4)
- 開発リーダの役割
- 運用リーダの役割
- 開発リーダと運用リーダーの役割の違い、関係性
- 外部のサービス開発・提供者リストの作成タイミング
- RFP(提案依頼書)の粒度と対応策
- RFP回答が理解できないときの対応
- IT導入実行計画書を策定する担当
- システム導入計画とIT 導入実行計画書の関係性
- 価値実現サイクルを回転させて実施する段階的な開発
- アジャイル開発(スクラム、契約形態)
- IT 資源配備・展開準備の留意点
アジャイル開発や外部委託との関係も含め、現実のプロジェクトマネジメントに沿った理解が必要でした。
価値提供・運用プロセス(P5)
- 価値提供・運用プロセスの活動
- 提供価値をどう維持するか
- IT サービス提供がアウトソーシングされている場合のSLM 推進の責任所在
- システム監査の実行手順
顧客にとっての価値をどう提供するかが問われていました。
提供価値検証プロセス(P6)
- 価値実現サイクル(C2)各プロセスへのフィードバック内容
- デジタル経営実行計画プロセス(P3)へのフィードバック内容
提供した価値を測定し、次の改善につなげる検証プロセスの重要性を理解しているかがカギです。
サイクルマネジメント(CB-1)
- サイクルマネジメントが対象とするサイクル
- ポートフォリオマネジメント
- サイクルマネジメントとプロジェクトマネジメントの違い
コミュニケーション(CB-2)
- 良好なコミュニケーション環境の構築に必要なスキル
ITと経営の橋渡しをする立場として、ファシリテーション力や対話力の重要性が強調されていると感じました。
モニタリング&コントロール(CB-3)
- モニタリング&コントロールが対象とするプロセス
単なる管理ではなく、進行状況を把握し、必要に応じて軌道修正する力が求められる領域です。
セキュリティ(CB-4)
- ランサムウェア対策
経営に影響するセキュリティリスクを、技術だけでなく運用や体制面からも理解することが必要でした。
組織学習(CB-5)
- 組織学習における経営者の役割
- 組織学習における従業員の動機付けを担う経営者
- 暗黙知を形式知へ変換する手法
人材育成や知識共有の仕組みをどう設計するかという、実務的で経営寄りの観点が特徴的でした。
まとめ
今回の試験を通して強く感じたのは、「不安や緊張は、しっかりとした準備でしか乗り越えられない」ということです。
サンプル問題を何度も解きながら、試験当日の流れをできるだけ具体的にイメージしておいたことで、本番も落ち着いて臨むことができました。
ITコーディネータ試験は決して簡単ではありませんが、その学習プロセスそのものが、ITCとしての第一歩になると感じています。
不安や焦りを感じるのは自然なことです。でもそれ以上に、「ここまで準備してきた自分を信じる力」が、合格へのいちばんの力になると思います。